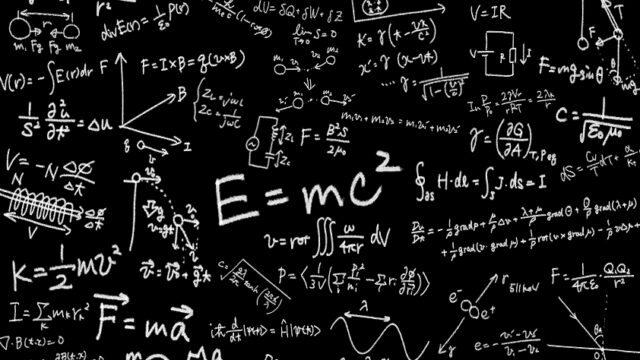【定期テスト】点数が伸びない子どもに足りない「3つの視点」
「毎日勉強しているのに、定期テストの点数が伸びない」
そんな悩みを抱える中高生と保護者の方は少なくありません。
学習習慣が身についているのに、思うような結果が出ないと、
「このまま頑張って意味があるのか」
と不安になることもあるでしょう。
しかし、定期テストで点数が伸びない理由は、単に努力不足ではありません。
むしろ「努力の方向がズレている」ことこそが原因になっているケースが多いのです。
この記事では、勉強習慣はあるのに成績が伸びない子に共通する「3つの課題」とその対策を解説します。
視点1:暗記だけで終わっている「インプット過多型」

課題の特徴
- 教科書やノートをひたすら読む
- ワークやプリントを“解いたつもり”で進めている
- 解答を写すだけで「分かった気」になってしまう
このタイプの学習は、頭に入れた知識がテストで「使えない」状態になりがちです。
対策:「アウトプット前提」で学習を組み立てる
- ワークを「テスト形式」で解く時間を毎日つくる
- 解いた問題は答え合わせ+なぜそうなるかの説明を自分で書く
- 家族や友人に「授業」をするように説明してみる
テスト本番に近い状態でアウトプットの練習を積むことで、知識の定着と活用力が大きく向上します。
視点2:全体像が見えていない「バラバラ学習型」

課題の特徴
- やみくもに勉強していて、どこを重点的にやればいいか分からない
- やった内容とテスト範囲が合っていない
- 試験直前になって「間に合わない」状態に陥る
計画性のない学習は、せっかくの努力が無駄になりやすく、モチベーションの低下にもつながります。
対策:「逆算型」で計画を立てる
- テスト範囲と試験日から逆算してスケジュールを作成
- 単元ごとに“やることリスト”を細かく分けて管理
- 苦手分野には多めに時間を割くなど、戦略的な調整を加える
「何を」「いつまでに」「どのくらい」やるかを可視化することで、迷わず勉強を進められるようになります。
視点3:理解が浅い「なんとなく理解型」

課題の特徴
- 授業は聞いているが、自分で説明できない
- ワークの答えは合っているが、理由を聞かれると答えられない
- 暗記に頼りすぎて、応用問題になると対応できない
定期テストでは「理由」や「プロセス」が問われる設問が多く、表面的な理解だけでは得点につながりにくくなります。
対策:「対話的な学び」で深く理解する
- 自分の言葉で説明する練習を取り入れる
- 解答のプロセスを一緒に検討できる相手(講師や友人)を持つ
- なぜ間違えたかを分析する「振り返り学習」を必ず行う
人に説明できるかどうかが、理解の深さを測る一つの指標です。
単に「解けた」ではなく「納得できた」状態を目指しましょう。
定期テスト対策に、オンライン家庭教師という選択肢

これらの課題は、どれも一人では気づきにくい・解決しにくいという共通点があります。
そんな時に有効なのが、オンライン家庭教師のサポートです。
東大個人指導塾「東大オンライン」の強み
- 現役東大生が生徒の弱点やつまずきポイントを見極めて指導
- テスト前に合わせたカスタマイズ授業が可能
- 勉強のやり方からスケジューリングまで総合的にサポート
- 完全1対1の個別指導で、表面的な理解ではなく「本質的な理解」を重視
画一的な指導ではなく、生徒一人ひとりの課題に寄り添いながら、定期テストでしっかり得点できる力を育てます。
まとめ:点数が伸びない理由を見極めて、正しい方向へ努力を

定期テストで点数が伸びないのは、努力が足りないからではありません。
- アウトプット不足
- 計画性の欠如
- 表面的な理解
この3つのどこに課題があるのかを見極め、正しい対策をとれば必ず結果はついてきます。
「勉強はしているのに伸びない」と感じているなら、一度オンライン家庭教師という形で学習を見直してみてはいかがでしょうか。
東大個人指導塾の「東大オンライン」なら、あなたの課題に合わせた学習の再設計が可能です。
無料体験から、お気軽にお試しください。